

現代の樽酒づくりで、大きな問題となっているのが樽職人の減少です。
このままでは樽酒文化が途絶えてしまう……。日本酒文化継承の一端を担ってきた老舗として、
菊正宗は未来へつなげる取り組みをはじめています。
樽酒づくりにおいて、「樽」は樽酒を生育する母体。いい樽があってこそ、いい樽酒が生まれるのです。ところが、時代の変化とともに樽製造会社が廃業していき、樽職人の数も減少するばかり。このままでは安定量を製造できないだけでなく、樽酒の存続も危うくなってきます。「続けるためには、自分たちでつくるしかない」。そう決断した菊正宗は、樽職人を雇い入れました。
自社での製樽は、必要数を確保できるだけでなく、樽の品質管理の徹底にもつながります。吉野杉という酒樽に向いた木材を取り寄せ、熟練の職人たちが樽酒用として仕上げる。“樽酒のための樽”で育むことで、「うまい!」といっていただける本物の樽酒がつくれるのです。

細く割った竹を樽の外周に合わせて結い、箍(たが)をつくる

箍(たが)となる竹は丸竹から割り、加工していく

15~18枚の側板を組み合わせて円筒状の樽に仕上げる

底の段差を削り、水平に整える

樽を支える箍(たが)7本が締められる

正直台を使い、樽づくりの要となる正直(しょうじき)をつくる

様子を見ながら鉋(かんな)で削り、仕上げていく
-

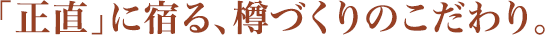
満ち渡る吉野杉の香りに圧倒される製樽場では、3人の職人たちが一年中、樽づくりを行っています。
箍(たが)を丸竹から割った竹で編み、側面の杉材をカンナで削って形成。しっかりと下準備をしたのち、ようやく樽は組み立てられていきます。くぎも接着剤も使わず、一滴も酒をもらさない樽をつくるためには熟練の技が不可欠。次世代へ技術を継承させるため、現在はベテラン職人のもとで若手も修行に励んでいます。
製造工程でもっとも難しいとされるのが、「正直」といわれる側板と側板が接する面づくり。この面が決まらないと側板がぴったり合わさった円筒状の樽に仕上げられないため、経験豊富な職人でさえ緊張する作業です。職人のこだわりが宿る「正直」と「正直」を合わせていい樽をつくる、樽酒の根幹をなしているものづくりへの信念が見えるような気がします。
樽材は、日本三大美林のひとつである吉野の杉。「節が少なく木目がまっすぐ通っていて香りがいい」ことから、酒樽にもっとも向いているといわれる吉野杉を菊正宗は江戸時代から使っています。
杉の産地で樽酒の風味が変わるのか? 菊正宗は吉野以外の杉で樽酒を製造したことがあります。いろいろな産地の杉で試みましたが、行き着いた先は「吉野杉が一番うまい!」。吉野に根づく大きな遺産は、今も樽酒のおいしさを支えてくれています。


